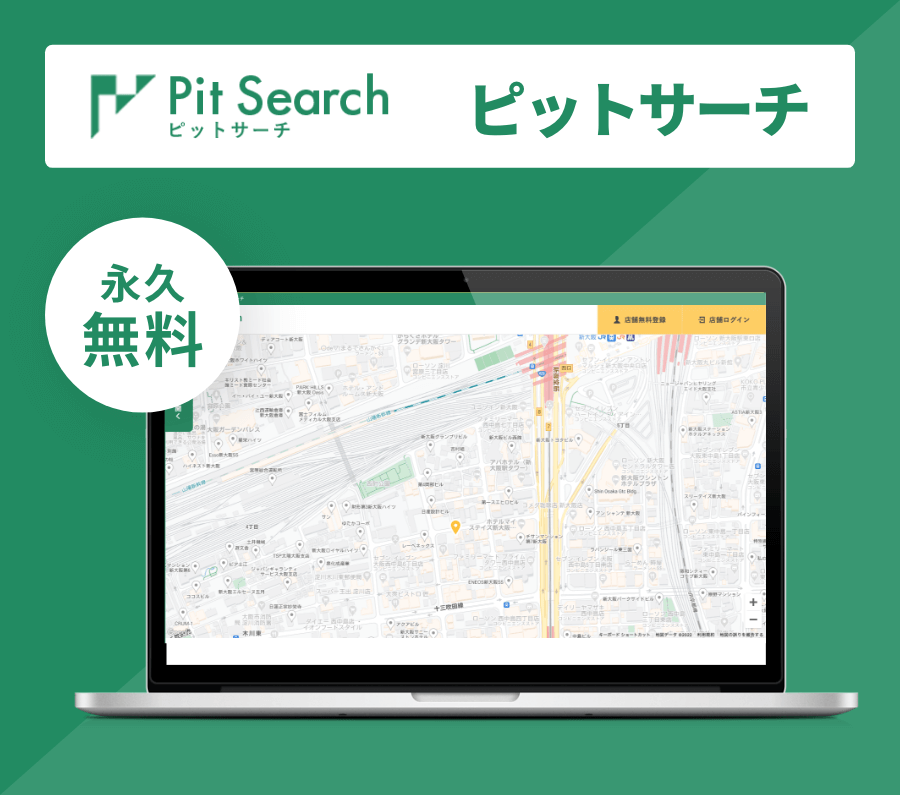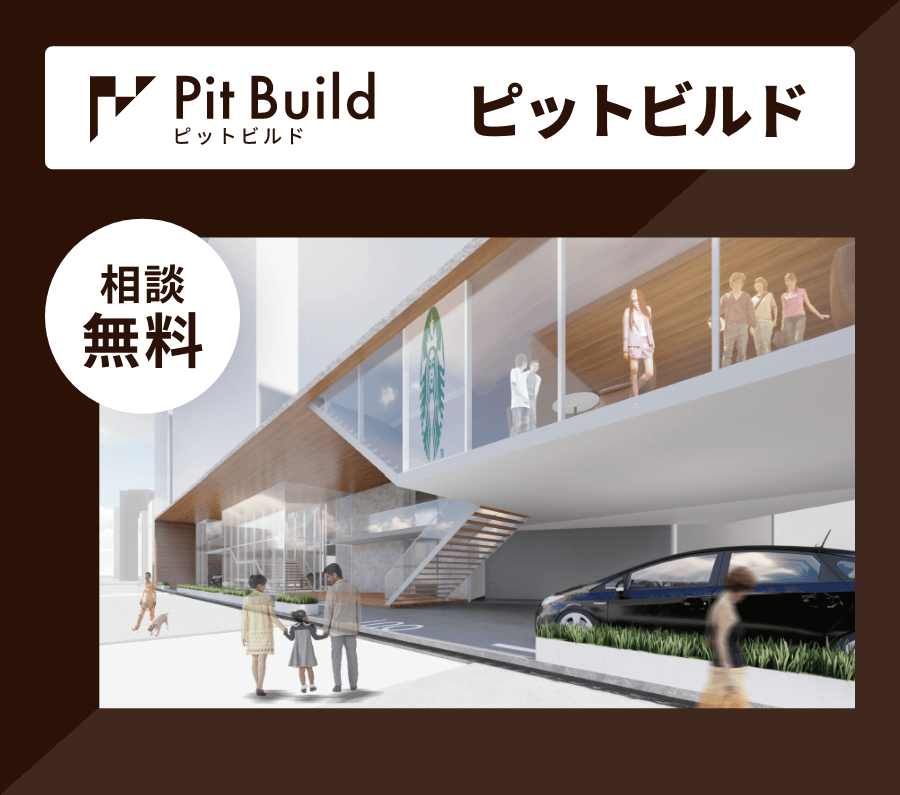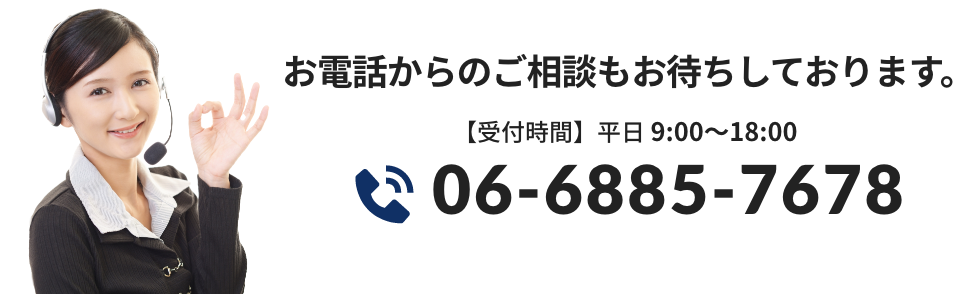【目次】
1 2021年における中古車市場の現状とは?
2 今後の中古車市場はどうなる?
2-1 「カーボンニュートラル」の一環で使用済車両の数を減らす取り組みが行われる
2-2 「トレーサビリティ・サービス」上陸で個人間での中古車売買が活発化する可能性がある
3 予測される中古車市場の変化における整備事業者のビジネスチャンスとは?
3-1 中古EV車の価値算定業務
3-2 中古車の品質保証事業
4 まとめ
2021年における中古車市場の現状とは?
日本自動車工業会が公開しているデータによると、2019年時点での中古車販売台数は699万台でした(※1)。2020年のコロナ禍では、半導体の納品遅れによる新車の納車数減が生じましたが、低価格かつ現物取引の中古車には一定の需要がありました(※2)。
現状の中古車市場は、ユーザーからの直接売買(下取りから買取りまで含む)もありますが、中古車販売ルートにおけるディーラーの割合が大きいと思われます。2014年時点で国土交通省が発表しているデータでは、古物商である同業者からのオークション(AA)取引が全体の94%と主な仕入れルート(※3)となっています。2021年現在も、取引ルートのほとんどをディーラーが担っていると考えられます。
中古車については、車両ごとの成約単価が上昇傾向にあり、オークションサイト「USS」のIR情報(※4)を参照すると2021年次は各月で前年比110%〜140%の間の単価となっています。2021年も引き続き、半導体不足・工場の稼働停止などによる新車の納品数減が懸念されます。その結果、中古車ニーズが高まり中古車購入をするユーザーが増える可能性が考えられますので、中古車の取引価格はまだ上昇する可能性もあるでしょう。
市場での取引が増えれば、自ずと中古車の価値算定の重要性も増すと予想されます。整備店としては、中古車を購入したい、もしくは所有している車を下取りに出したいと考えるユーザーに対し、中古車の価格の算定や事故履歴などに関する情報提供を行うケースも増えるかも知れません。
今後の中古車市場はどうなる?

社会変容により今後の中古車市場もさらに変化していくと考えられます。現在、中古車市場に大きく影響を及ぼす要素として、脱炭素社会を目指す「カーボンニュートラル」や欧米で主流な「トレーサビリティ・サービス」などが挙げられます。
「カーボンニュートラル」の一環で使用済車両の数を減らす取り組みが行われる
カーボンニュートラルとは温室効果ガス排出量を減らすための取り組みで、日本でも政府主導で計画しています。日本中古自動車販売協会連合会は、カーボンニュートラルに向けて温室効果ガス排出を抑えるために新車の製造台数が減少し、自動車をなるべく長く使うよう社会全体が変容していく可能性があると分析しています(※5)。そのため、中古車市場でも自動車の新規製造数を減らすための施策が行われるかもしれません。例えば、現存する車両を少しでも長く使い使用済み自動車を減らすために車両オーナーに予防点検や整備を促したり、使用済みとなった車両でも中古部品として使えるパーツを再利用することを促進したりといった取り組みです。
※車両整備業者のカーボンニュートラルへの心構え
「トレーサビリティ・サービス」上陸で個人間での中古車売買が活発化する可能性がある
欧米では、日本に比べ個人間での中古車売買が活発に行われているのが特徴です。日本では個人間販売の割合が6%なのに対し、アメリカが29%、英国は42%となっています(※3)。欧米で個人間取引が盛んな理由として、車両の走行距離や事故履歴がわかる「トレーサビリティ・サービス」が挙げられます。国土交通省は、日本でもトレーサビリティ・サービスに対する潜在的なニーズがあると分析しており、日本でも今後IT技術が進展すれば、C2Cビジネスとして個人間での中古車販売が盛んになるかも知れません。
予測される中古車市場の変化における整備事業者のビジネスチャンスとは?
以上を踏まえ、今後中古車関連で車両整備事業者の皆さまがビジネスを展開していこうと考えた場合「中古車の予防点検・整備の需要増」「中古車の品質保証事業」に、より大きなチャンスがあると予想されます。
中古EV車の価値算定業務
中古車市場では、前述のようにカーボンニュートラルの影響を受け、車両を少しでも長く使うための予防点検・整備の需要が高まると考えられます。特に、今後の日本ではEV車のシェアの拡大が予想されています。しかし、EV車の価格は調達コスト全体の24%(※6)を占めるリチウムイオン電池の影響を受けるため、経年による劣化も起こりやすく、中古車として販売する場合のネックとなります。そのため、中古のEV車においては駆動バッテリーのチェック・交換に対する重要性が増し、ガソリン車以上に予防点検・整備や価格算定サービスの需要が拡大するかも知れません。
車両整備事業者としては、いち早く中古のEV車のバッテリー性能や修理情報などをユーザーへ提供するサービスを行えば、他者との差別化に繋がり、自社へのロイヤルティをより向上させられるでしょう。
中古車の品質保証事業
もし日本で中古車の個人間販売が盛んになれば、販売価格はディーラー経由よりも安価な一方、品質が保証されないことに不安を抱くユーザーも増えるはずです。そこで車両整備事業者が間に入りチェックを行う、もしくは事業者自ら中古車販売を代行するサービスが成り立つ可能性があります。この際、「事故履歴の参照」「同車種間での相対評価 」「メーター巻き戻し(走行距離)」「整備情報」などの提供を行うトレーサビリティ・サービスを同時に実施すれば、整備店としての付加価値はより向上するでしょう。日本では、車両の整備履歴情報を直ちに手に入れるためのシステム化がまだ十分には行われていませんが、安価でトレーサビリティ・サービスを提供できるようなシステムが登場すれば、中古車の個人間販売は増える可能性があります。
まとめ
中古車市場は現状でも巨大なマーケットであり、カーボンニュートラルや欧米でメジャーな存在であるトレーサビリティ・サービスを踏まえると、今後は中古車に対するユーザー側のニーズもより高まっていくでしょう。
車両整備事業者にとって、中古車関連で今後さらに自社ビジネス拡大のチャンスが生まれる可能性があり「中古車の予防点検・整備業務」「中古車の品質保証事業」などが考えられます。
大阪・兵庫を中心に車両販売・整備事業の再開発を行うビズピット株式会社では、整備履歴が参照可能になるクラウドサービス「ピットチケット」を開発中です。より効率的に整備情報を入手したいと考えているものの、ご自身で対応していくことに不安を抱えていらっしゃる方はぜひお問い合わせください。
【引用】
※1
・日本自動車工業会
https://www.jama.or.jp/industry/four_wheeled/index.html
※2
・Responce
https://response.jp/article/2021/05/06/345568.html
※3
・国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001063634.pdf
※4
・USS
https://www.ussnet.co.jp/ir/library/monthly/index.html
※5
・日本中古自動車販売協会連合会
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/carbon_neutral_car/pdf/003_04_00.pdf
※6
・webCG
https://www.webcg.net/articles/-/44062