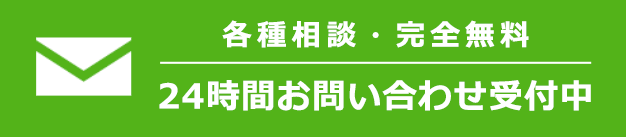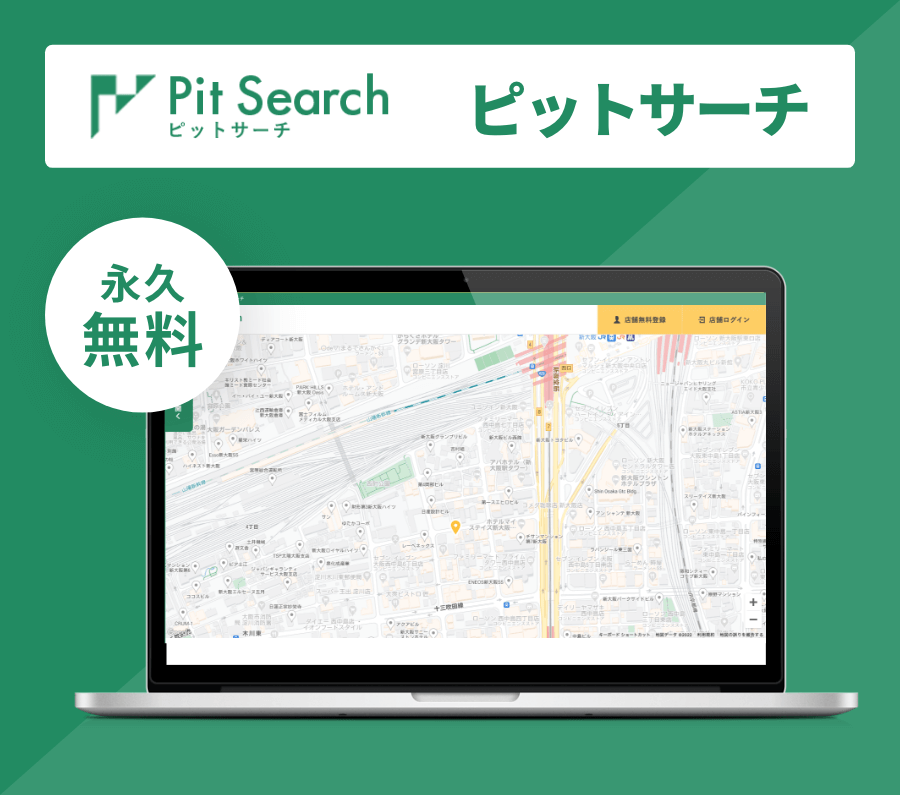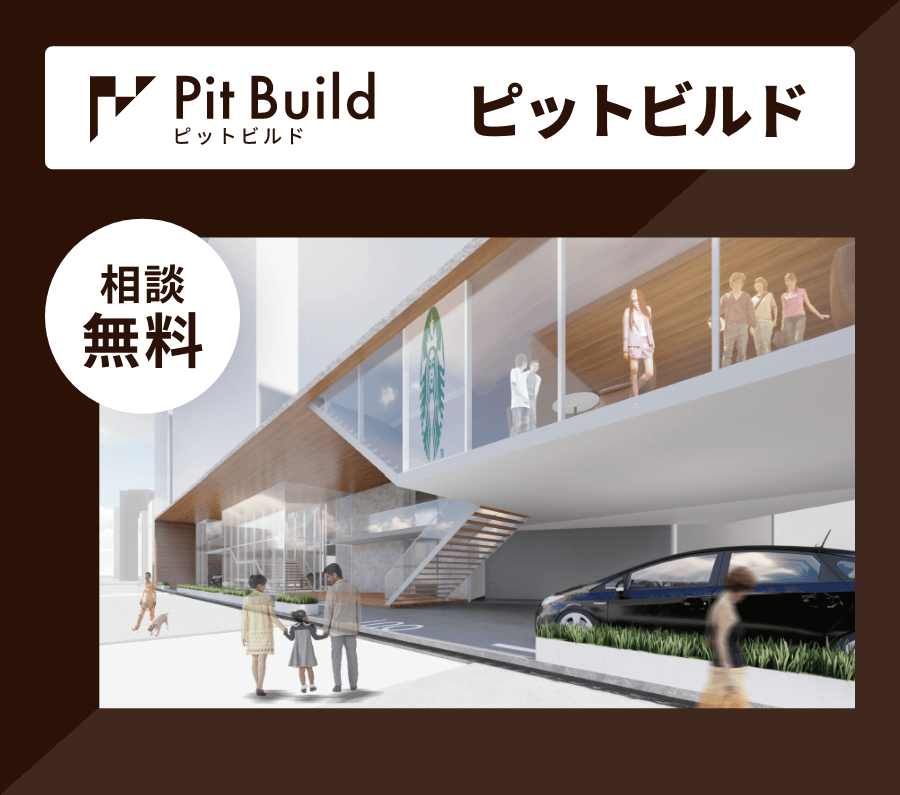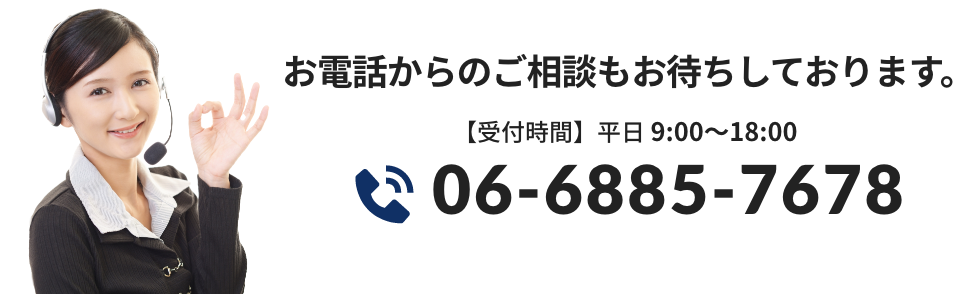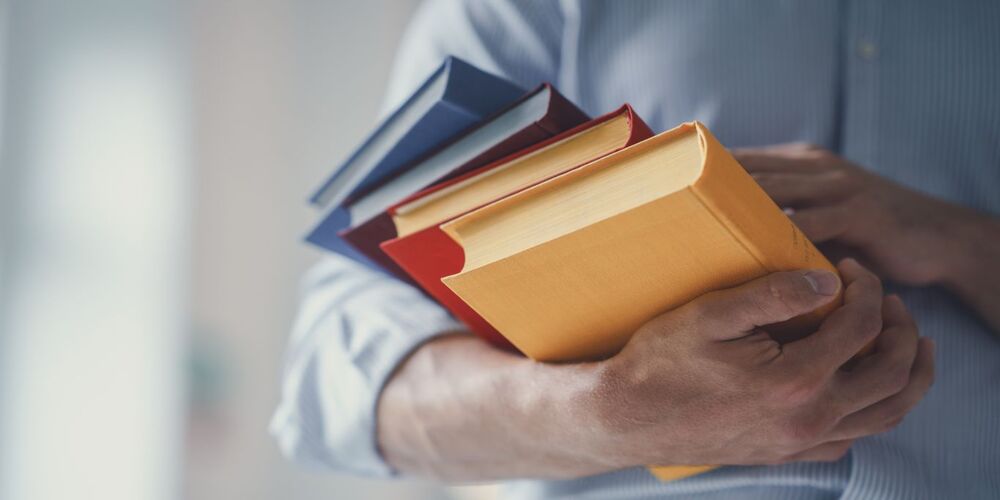
整備業界では慢性的な人材不足が続いており、外国人雇用が注目を集めています。
しかし、「そもそもどのような制度があるのか?」「採用までの流れは?」と疑問に思う経営者の方も多いのではないでしょうか?
本記事では、外国人整備士の雇用に関する基礎知識を体系的に解説します。
この記事で分かること
- 外国人雇用の必要性と業界の現状
- 外国人材を雇用するための制度と仕組み
- 採用プロセスと成功のポイント
なぜ今、整備業界で外国人雇用が必要なのか?
整備業界の人手不足と高齢化の進行
自動車整備業界では、深刻な人手不足が続いています。
特に地方の整備工場では若手人材の確保が難しく、今や「人がいないから仕事が受けられない」という状況すら発生しています。
その背景には、整備士の高齢化が大きく関係しています。
日本自動車整備振興会連合会(日整連)によると、整備士の平均年齢は年々上昇傾向にあり、40代後半〜50代のベテランに頼る構造が続いています。若年層の採用が難しく、世代交代が進まないことが現場の課題です。
求人倍率の上昇と採用難
令和7年に発表された厚生労働省のデータでは、自動車整備士の有効求人倍率は5倍以上と非常に高く、1人の求職者を5社以上が取り合う状況です。特に中小の整備工場では、待遇や立地面でディーラーや大手整備工場に太刀打ちできず、「一年間募集しても応募がゼロ」ということも珍しくありません。こうした採用難に直面する中、外国人材への関心が高まりつつあります。
外国人雇用が注目される背景
整備業界で外国人雇用が注目される理由の一つが、2019年に始まった「特定技能」制度です。これにより、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、即戦力として整備業に従事できるようになりました。
また、他業種(介護・外食・建設など)ではすでに外国人雇用が定着しており、「整備業界でも十分に通用する」という認識が広がっています。
実際に、特定技能で整備士を受け入れた工場では、定着率の高さやまじめな勤務態度が評価され、「もっと早く導入すればよかった」との声も少なくありません。
今後の市場動向と採用戦略
今後、日本の少子高齢化が加速する中で、若年層の労働力はさらに減少すると予測されています。こうした中、外国人整備士の確保は、単なる日本人整備士の代替ではなく中長期的な戦略の一環として位置づける必要があります。
制度の変更や受け入れ条件の見直しも進んでおり、早めに外国人雇用に取り組んだ工場ほど優位に立つことができます。実際、先行して外国人整備士を採用した事業者は、継続的な育成体制や多文化共生の仕組みを整えることで、戦力としての定着に成功しています。
関連情報:なぜ今、整備業界で外国人雇用が必要なのか?**(準備中)**
整備士に適用できる外国人雇用制度の全体像
外国人が働ける在留資格

外国人を整備士として雇用するためには、適切な在留資格を取得することが必要です。日本にはさまざまな在留資格があり、各資格によって働ける職種や雇用形態が異なります。
整備業界で外国人を採用する場合、特定技能制度と技能実習制度が代表的な制度です。
在留資格を取得するには申請手続きが必要で、資格に応じた基準を満たす必要があります。例えば、特定技能の場合は、日本語能力や専門的な技能が求められ、技能実習制度では、技能を学びながら実務経験を積むことが求められます。
整備士に関係する主な制度:特定技能・技能実習
整備業界で外国人を雇用する場合、特に注目すべきは特定技能、技能実習の制度です。それぞれの制度の概要と特徴は以下のとおりです。
特定技能
特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、整備業界に従事できるように設けられた制度です。
この制度は、長期的な雇用を見越しているため、特定技能1号は最長5年ですが、特定技能2号を取得することで、5年以上の契約が可能であり、その後の更新や家族の帯同も可能です。
特定技能は、他の資格よりも柔軟性が高いことから、近年多くの整備工場が注目しています。
技能実習
技能実習制度は、技能を学びながら働くことを目的とした制度です。
特定技能とは異なり、最長5年までしか滞在できませんが、次に説明する特定技能制度に移行することで、雇用期間の延長も可能です。日本の技術や文化を学んだ後、自国に戻って技術を還元することを目的としています。整備業界でも、若手技術者を受け入れ、技術力を向上させるために活用されています。
| 制度名 | 目的 | 雇用期間 | 特徴 |
| 特定技能 | 人手不足が深刻な 特定産業分野における人材確保 | 5年以上可能 | 長期雇用、 家族の帯同可 |
| 技能実習 | 開発途上国への技能・技術・知識の 移転による国際協力 | 最長5年 | 自国への技術移転を目的、 若手を対象 |
それぞれの制度には、整備工場のニーズに応じた適切な選択が必要です。
特定技能は長期的な雇用を目的としているため、継続的な業務の安定が期待できます。
技能実習は、若手育成や技術伝承を目的とした短期的な雇用に適しています。
関連情報:
外国人雇用の全体像がわかるガイド**(準備中)**
外国人雇用の種類と制度まとめ**(準備中)**
外国人が働ける在留資格とは?**(準備中)**
外国人採用の流れと関係機関の役割
整備工場で外国人を採用するためには、各制度で決められた方法や順序で手続きを行う必要があります。
採用から受け入れまでのステップ
外国人整備士の採用には、まず在留資格の取得やビザ申請を行い、その後、採用契約を結びます。さらに、労働条件や住居の手配など、入国後のサポートが必要です。
監理団体・登録支援機関の役割
監理団体は、技能実習生の受け入れに関する全般的な監督を行い、登録支援機関は外国人の生活支援や労働環境の整備を担当します。これらの機関の協力が、円滑な外国人採用には不可欠です。
労務トラブルを防ぐために注意すべき点
雇用契約書の明確化、労働時間や給与の適切な管理が重要です。特に、文化的な違いや誤解を避けるため、労働条件をしっかりと説明し、常にフォローアップを行うことが求められます。
詳細については、以下の記事でさらに学べます。
関連情報:
雇用の流れと関係者**(準備中)**
登録支援機関の役割とは**(準備中)**
外国人整備士雇用のために知っておくべきポイント
外国人整備士を長期的に活躍させるためには、単に採用するだけでは不十分です。
教育体制、文化的なサポート、そして適切な労務管理が重要なポイントです。
しかし、外国人雇用においてはよくある誤解や注意すべき点もあります。これらを理解しないまま進めてしまうと、労務トラブルや定着率の低下につながることもあります。
外国人雇用におけるよくある誤解と注意点
外国人雇用を始めた際に、「安く雇える」「支援機関に任せておけば安心」といった誤った認識を持っている経営者が多く見受けられます。
しかし、実際には技能実習制度の本来の目的や労務管理のルールを経営者自身が理解しておくことが不可欠です。外国人整備士を適切に育成し、定着させるためには、制度の正しい理解と適切な支援が必要です。
支援機関や労務管理の重要性
登録支援機関に頼りきりではなく、現場の管理者が積極的に関与することが、外国人整備士の定着率を高めます。また、文化的なギャップや生活面のサポートが定着に大きく影響します。労務トラブルを防ぐためにも、適切な契約管理や生活支援を心がけることが重要です。
定着支援の施策とコミュニケーション
外国人整備士の定着には、業務研修だけでなく、職場環境やコミュニケーション体制の改善が求められます。定期的なフィードバックや日常的なサポートを通じて、職場での問題を早期に発見し、解決することが大切です。
関連情報:よくある誤解と注意点|知らないと損する外国人雇用の落とし穴**(準備中)**
よくある疑問、質問と成功事例から学ぶ
よくある疑問(費用感/言語/どの制度?)
外国人整備士を雇用するにあたって、特に気になるのは費用感や言語の壁、そしてどの制度が自社に最適かという点です。
実際に、外国人を雇用するためのコストは、制度や規模により大きく異なります。また、言語の障壁もスムーズな業務遂行に影響を与える要素ですが、近年は日本語教育支援が充実しており、克服する手段も増えています。自社の整備工場にどの制度が最適かについては、企業の規模や求めるスキルセットに応じて、特定技能や技能実習などの選択肢があります。これらの疑問点を解消するために、各制度の特徴や適用範囲をしっかり理解しておくことが大切です。
成功している整備工場の共通点
外国人整備士を積極的に受け入れ、成功を収めている整備工場にはいくつかの共通点があります。研修制度の充実がその一つです。特に、技術研修に加えて、日常業務で必要となる日本語教育や文化理解をしっかりと行うことで、作業効率や職場環境の改善が進んでいます。また、継続的なサポートやフィードバック体制を整えることで、外国人スタッフの定着率を高めています。こうした成功事例から学ぶべき点は、雇用前の準備が重要であり、受け入れ体制を整えることが成功への近道だということです。
失敗事例とそこから得られる教訓
失敗事例もまた貴重な学びの材料です。
特に、コミュニケーション不足や制度理解不足から生じるトラブルは多くあります。
また、労働契約や雇用条件についての認識のズレが後々トラブルを引き起こす原因になることもあります。
これらの問題を防ぐためには、事前の準備や契約内容の明確化、そして現場での定期的な対話が重要です。
失敗を避けるためには、最初からしっかりとしたフレームワークを作り、問題が起きた際にはすぐに対応できる体制を整えておくことがカギです。
関連情報:Q&A:外国人雇用を検討し始めた経営者のための10の疑問解決**(準備中)**
まとめ:外国人整備士の雇用は制度理解と継続的な支援が成功のカギ
日本の整備業界では人手不足と高齢化が進み、外国人整備士の雇用が現実的な選択肢となっています。中でも、「特定技能」と「技能実習」という2つの制度が主に活用されており、それぞれ目的や特徴が異なるため、自社のニーズに合わせた制度選定が重要です。
雇用に関しては、在留資格の取得や受け入れ体制の整備、関係機関との連携など多くのステップが必要です。特に、登録支援機関や監理団体といったパートナーの選定と協力体制が、スムーズな採用と定着の鍵を握ります。
また、「安く雇える」「支援機関に任せておけばよい」といった誤解は、トラブルや早期離職の原因となり得ます。文化的な違いや生活面への配慮を含め、現場での丁寧なフォローと継続的な支援が不可欠です。
外国人整備士の雇用を成功させるためには、制度の正しい理解と、自社に合った受け入れ体制づくり、そして何より「人材育成」という長期的な視点が求められます。