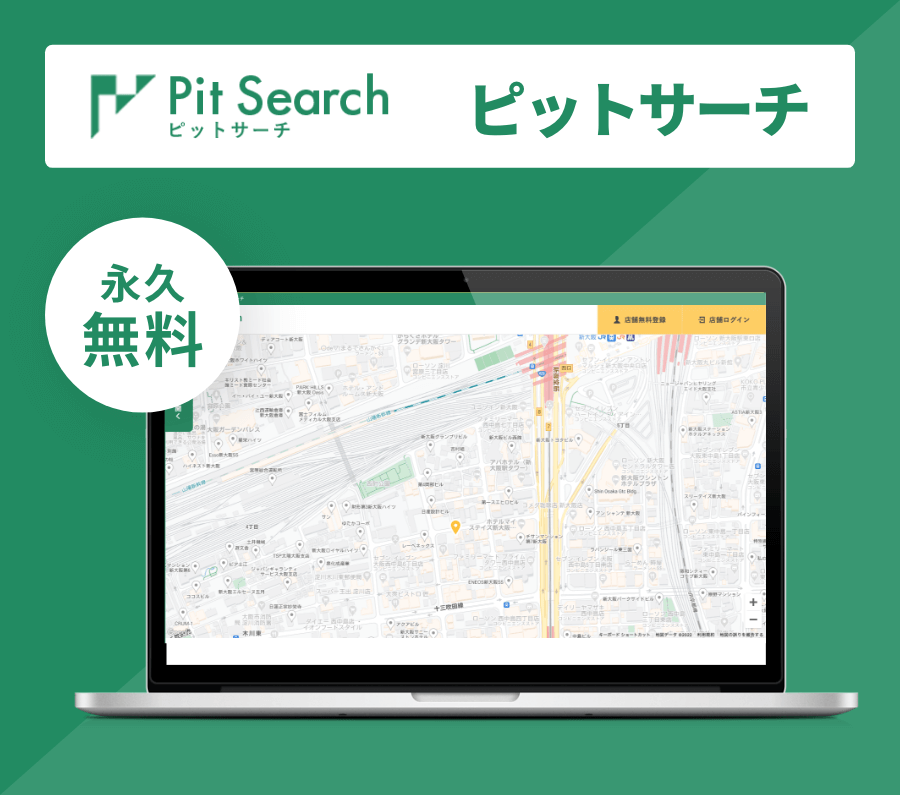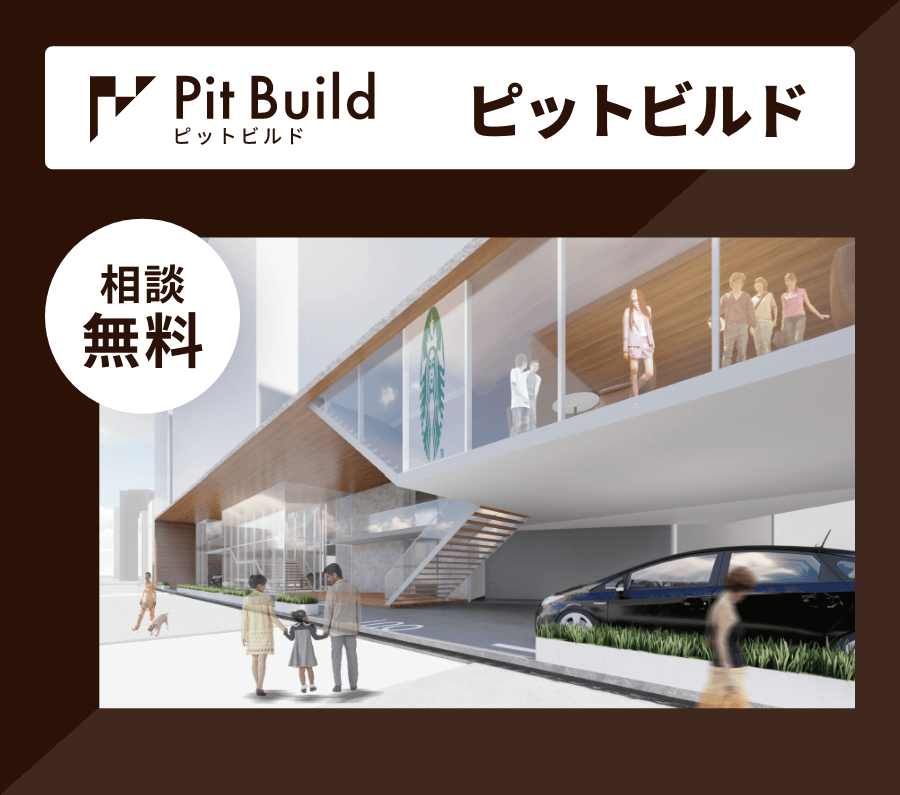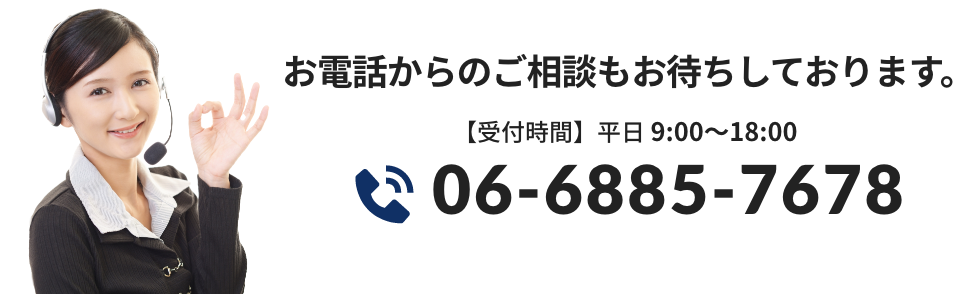本稿では、次世代に必要となる技術や、ツール導入に伴い想定される悩み、そしてその悩みを解決するアイディアをご紹介します。参考にしてください。
そもそもOBD(車載式故障診断装置)とは?
OBDとは、「On Board Diagnostics」の略称であり、「車載式故障診断装置」を意味する言葉です。自動車はあらゆる機能を正常に作動するために多くのセンサーを備えており、各センサーからの信号に基づきECU(Electronic Control Unit)が最適な制御を行っています。ECUとはエンジンやトランスミッション、エアバッグなどに備えられている電気制御装置のことです。
各センサーや電気配線などに異常が発生した場合は、ECUが異常信号を検知し、故障コードを自動で記録するようになっています。つまり、OBDとは自動車に異常が発生したときに、ECUが自ら行う故障診断装置のことです。
OBDの故障コードを読み取るためには、外部診断機(スキャンツール)を使用します。多くの自動車は運転席付近にOBDポートという、スキャンツールを接続するためのコネクタを備えているめ、OBDポートとスキャンツールを接続することでOBDの情報を読み取ることが可能です。スキャンツールで読み取った情報を活用することで不具合系統を絞り込めるため、自動車の故障解析に役立っています。
OBD車検(点検)とは?
OBD車検(点検)とは、OBDを活用した新たな検査方式です。OBD検査の対象となる車両は検査の際に、スキャンツールで故障コードの有無の確認します。故障コードは「DTC(Digital Trouble Code」と呼ばれ、DTCの中でも保安基準不適合となる故障コードは「特定DTC」と呼ばれています。
特定DTCはあらかじめサーバーに蓄積されており、OBD検査時の車両から特定DTCが検出されていないか確認を行います。車検時に特定DTCが検出された場合は不合格となるため、該当箇所の故障解析や修理を行い、特定DTCが検出されない状態で再度検査を行う必要があります。
OBD車検(点検)は2024年10月より義務化
2024年10月からの車検では、車検証の備考欄に「OBD検査対象」などの記載がある車両は、今までの検査項目に加えてOBD検査を行う必要があります。
OBD検査の対象となる車両は、国産車は2021年10月以降の新型車(フルモデルチェンジ車)、輸入車は2022年10月以降の新型車(フルモデルチェンジ車)です。
OBD車検(点検)が義務化された理由
OBD車検(点検)の義務化には、自動車の電子制御の導入が進んでいることが理由として挙げられます。自動車に電子制御システムが搭載されるケースは増え、自動ブレーキや駐車のサポートなどが日常的に利用されるようになりました。しかし、車検に必須とされている項目のなかに、電子制御に関する検査項目はありません。
そのため仮に電子制御システムに異常があっても、車検をパスして使用することができてしまうのです。電子制御の異常を検知するのは熟練の整備士でも難しく、自動車に搭載されている警告ランプが作動しない限り、不具合の判別はできないとされています。そこでOBD車検(点検)を義務化して、電子制御システムの異常をいち早く検知する体制づくりが進んでいます。
これからOBDはどう変わっていく?
これからOBDは、より精度の高い情報を記録できるようになることが期待されます。OBDがより多く、細かい情報を記録できることで故障解析を容易に進められるようになるでしょう。
一方で、自動車整備事業者には、より高度な故障解析能力が求められます。電子制御装置の故障解析は、OBDの情報を解析できないと不具合箇所を絞り込むことが困難となります。自動車は以前から機械制御から電子制御に変わってきていますが、近年はさらに電子制御の高度化・複雑化が進んでいるため、自動車整備事業者は新たな知識を習得し続ける必要があるでしょう。
特にOBD車検で特定DTCが検出された場合は、故障解析を行い不具合原因を解消しなければ、車検を完了させることもできなくなってしまいます。
OBDの拡がりに対する自動車整備事業者のメリット
OBDが普及することによって、電気系統の不具合を事前に察知したり、故障解析をスムーズに進められるようになったりといったメリットがあります。自動車の電子制御が高度化する中でOBDを活用した点検や故障解析を高いレベルで行えるようになれば、お客様の安心感や信頼感にも繋がるでしょう。
また、どうしても自社で故障解析が難しい場合などは、ディーラーなどに問い合わせたり、修理を委託することがあるでしょう。OBDの情報から不具合箇所の推定を行うこともできるため、データーのやりとりだけで故障解析が進められるケースも想定されます。
OBD車検(点検)で行うこと
OBD車検(点検)の際には、事業者が実施すべきとされる項目がいくつかあります。事前にOBD車検(点検)で行う内容を確認し、必要な作業を明確にしておくことがポイントです。以下では、OBD車検(点検)で実施する内容を解説します。
車両からDTCデータを取り出す
サーバーに情報を送信してECU情報の照会が完了したら、車両からDTCデータを取り出します。続いてECU情報に基づいて検査車両のDTCが確認され、データ通信によって情報を取得します。DTCの検出結果は、サーバーとアプリへ送信され、次の判定に活用されます。
特定DTCはOBD車検(点検)において、故障の内容や存在を確認するために用いられます。
特定DTCに該当するのか判定する
車両のDTCデータを読み込んだら、機構サーバー内で特定DTCの情報と照合し、検査の合否判定を実施します。特定DTCに該当すると判断されるか否かで、OBD車検(点検)における合否が決まる形になります。特定DTCにはさまざまな種類があり、詳細は国土交通省の「特定DTCの詳細定義について」で確認可能です。
結果を確認する
車両のDTCデータと特定DTCの照合が終わると、アプリに合否判定が出ます。合格の場合には電子制御に問題はないと考えられるため、特別な対応は不要となります。不合格だった場合には、具体的な問題を追及し、必要に応じた修理対応などを実施します。特定DTCは異常の大小に関わらず、検出された時点で不合格判定を下します。
一方、特定DTCの合否判定で、「通信エラーが原因の不合格」が発生することが懸念されます。OBDを読み取る際に通信エラーが発生した場合でも不合格判定となるため、常にスキャンツールなどの機器や通信環境を整えておくことも重要になるでしょう。
まとめ
2024年10月からOBD車検が始まります。OBD検査対象車両は決められた方法で、OBDから特定DTCの有無を確認し、保安基準の適合性を判断する必要があります。指定整備事業者はスキャンツールなどの機器やアプリ、通信環境を整えるだけでなく、どのような手順でOBD検査を進めるのか把握しておく必要があります。
また、特定DTCが検出された場合は保安基準不適合となるため、適切な故障解析と修理が必要です。自動車の電子制御装置は多様化しているため、今後の自動車整備事業者はOBDを使いこなし、新技術への対応を行うことが求められます。
OBD自体はOBD検査対象車両だけでなく、以前の車両にも搭載されています。OBDを使いこなすためには高度な知識や技術が必要ですが、習得できれば自社で幅広い車両の点検や故障解析を実施できるため、自動車整備事業者にとってもメリットは大きいでしょう。
参考記事について
https://www.mlit.go.jp/common/001255279.pdf