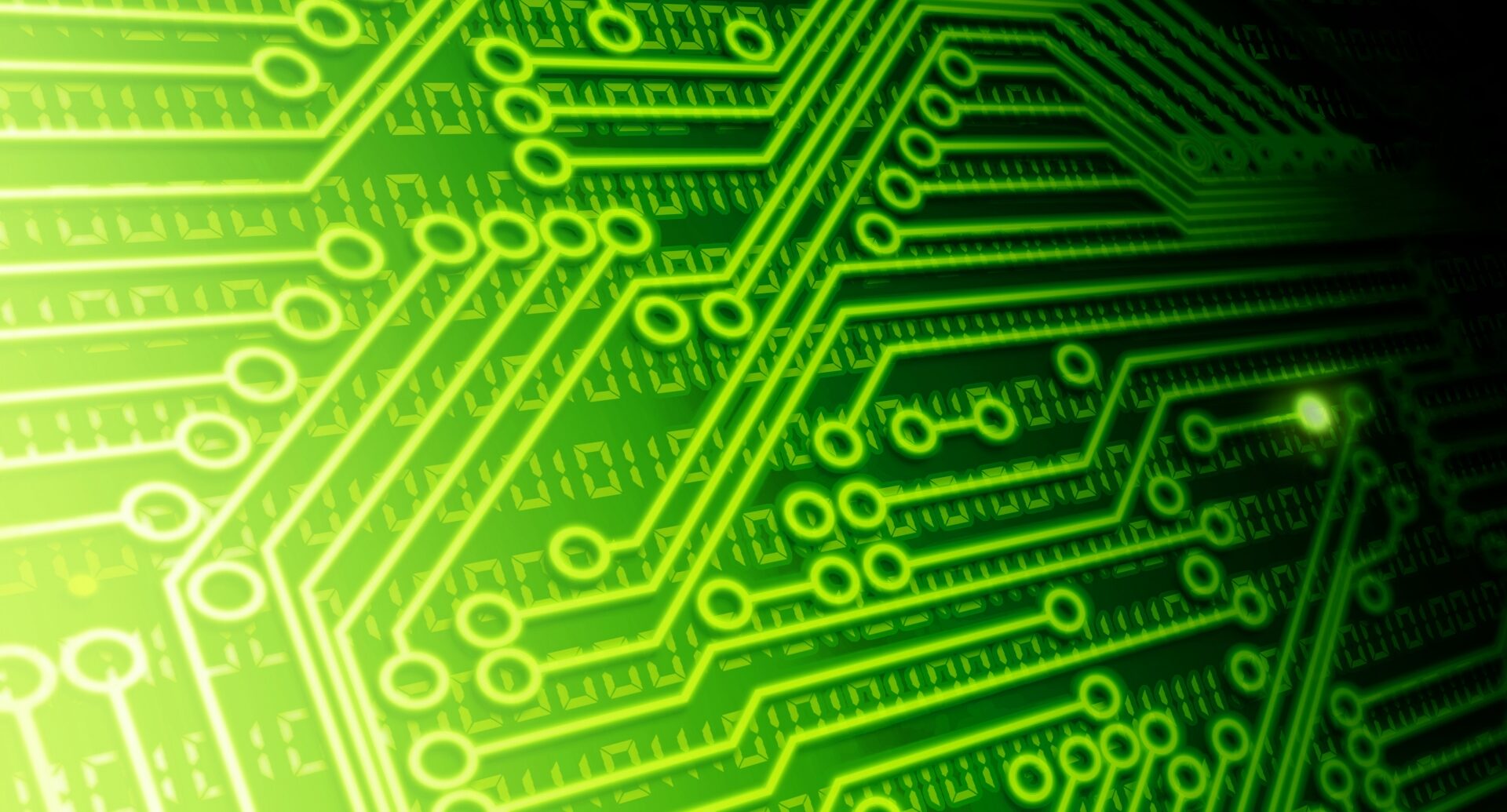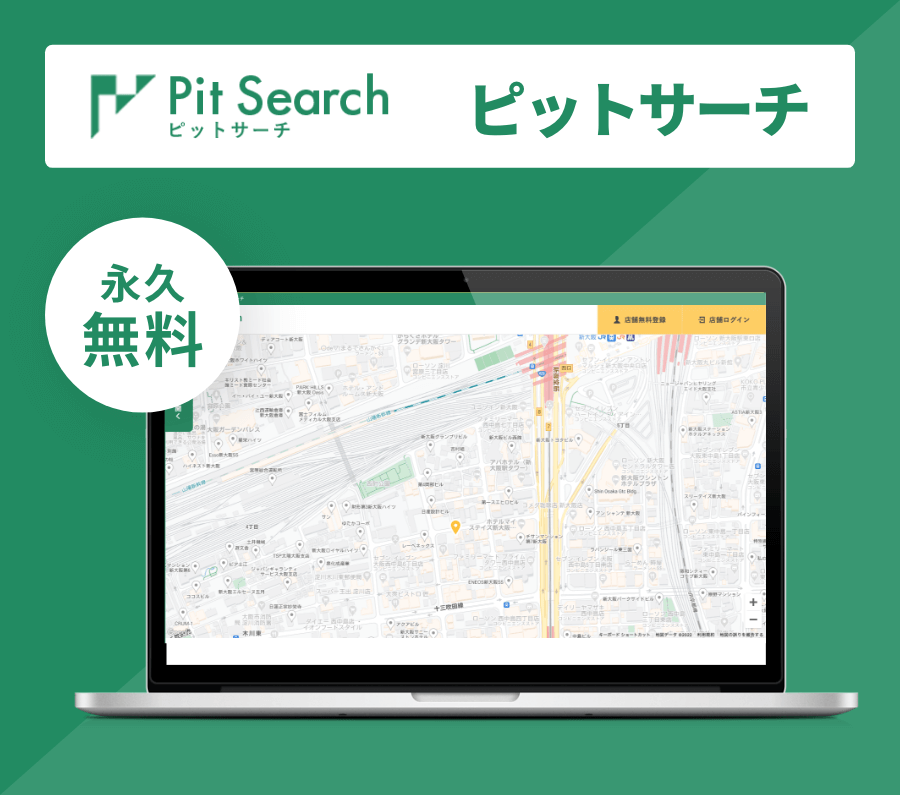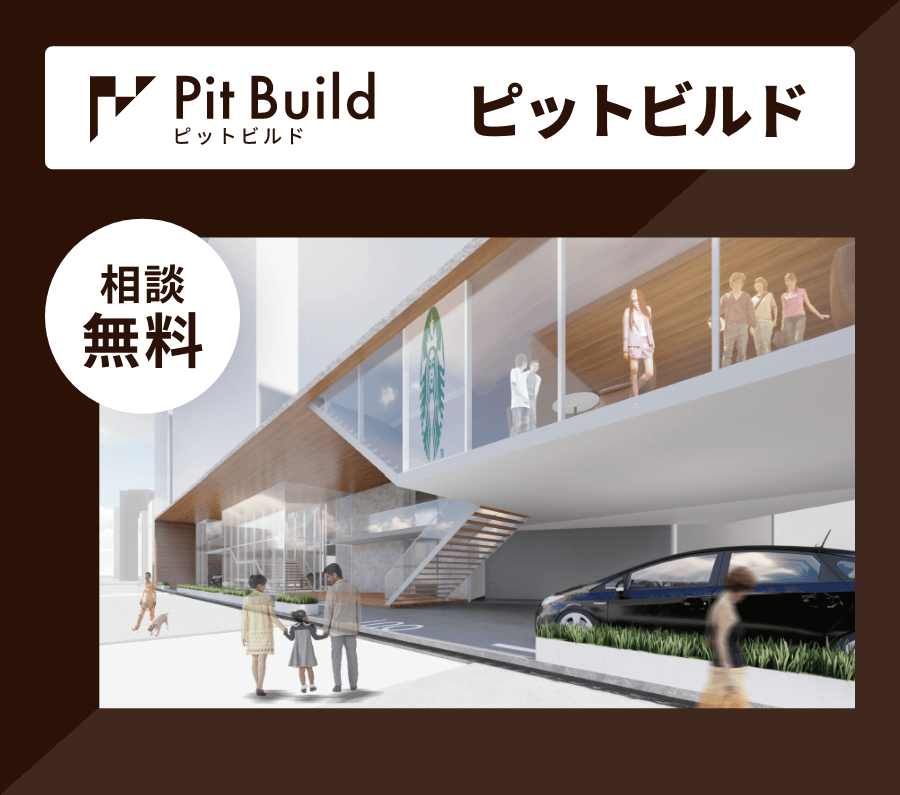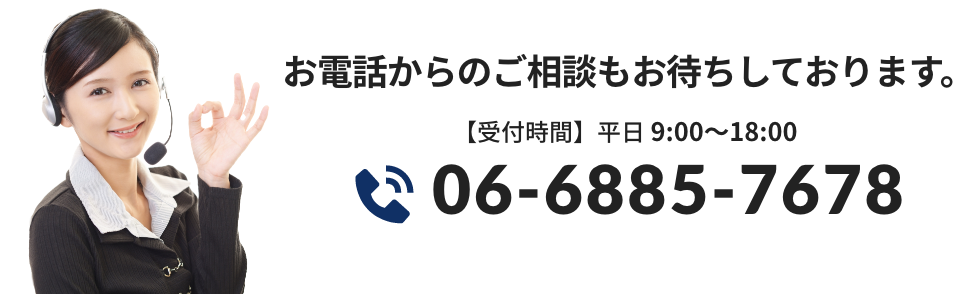自動車継続検査(以下車検)の領域においてもそれは例外ではありません。整備業者・ユーザー双方の負担軽減を図るため、IT技術の導入によって車検証をICカード化し、車検の手続きフロー全体をワンストップサービス化することが政府主導で進められています(※1)。
本稿ではそんな車検のIT化について、実際の導入後の業務の変化などを交えて紹介しますので、大阪・兵庫の自動車整備業者の皆さまのお役に立てば幸いです。
車検証のICカード化(電子化)の変更点
2023年1月4日から、普通自動車の車検証はICカード化(電子化)によって、さまざまな点が変更されています。自動車整備工場は変更点を確認し、適切な対応を取る必要があります。以下では、車検証のICカード化(電子化)による主な変更点を解説します。
行政の委託を受けた認定工場でできること
2023年1月から、行政の委託を受けた認定工場では、「記録等事務委託制度」によってさまざまな業務が可能となっています。従来、指定整備事業者は車検のOSS申請後に運輸支局等へ来訪し、新旧車検証の交換や検査標章を受け取る必要がありました。しかし、電子車検証の場合は、委託を受けた認定工場がOSS申請を実施し、更新可能通知・印刷可能通知をオンラインで受けることで、運輸支局等へ来訪しなくてもICタグの記録や検査標章の印刷を自社で行うことが可能です。
委託先となる事業者については、「継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検査証の変更記録に関する事務を運輸支局長等が一定の要件を備える者(指定整備事業者、行政書士等)」と定められています。
特定記録等事務と特定変更記録事務の2種類が設けられた
記録等事務委託制度には、「特定記録等事務」と「特定変更記録事務」の2種類が設けられています。特定記録等事務の対象手続きには「継続検査」が含まれ、申請方法は電子申請(OSS申請)となっています。特定変更記録事務に関しては、変更登録と移転登録が対象手続きとなり、所有者の氏名や住所などの券面変更を伴わない場合のみ対応可能です。
こちらも申請方法は電子申請(OSS申請)のみとなるため、オンラインでの申請が可能です。普通自動車における記録等事務委託制度はすでに始まっていますが、軽自動車に関しては2024年1月から開始予定となっています。
車検証閲覧アプリが必要
電子車検証には、従来の車検証にあった事項の一部が記載されておらず、ICタグに記録されています。電子車検証の券面に記載されていない事項は、「自動車検査証の有効期間」「所有者の氏名・住所」「使用者の住所」「使用の本拠の位置」「備考欄事項の一部」です。
上記の情報を確認するためには、「車検証閲覧アプリ」を使って内容を閲覧する必要があります。ただし、電子車検証発行時に、ICタグ内の情報も記載されている「自動車検査証記録事項」という用紙も同時に発行されます。
電子車検証のICタグの読み取る場合は、汎用のカードリーダーを使ってPCで読み取る方法や、読み取り機能付きのスマートフォンを使う方法があります。車検証閲覧アプリは国土交通省が2023年1月から配信を開始し、「車検証原本を所持する者」および「提示を受けられる者」を利用対象者としています。
車検証閲覧アプリには、「車検証情報の閲覧」「車検証情報ファイルの出力」「リコール情報などの確認」機能が備わっています。また、車検の有効期限が近づくと、更新時期をアプリの通知を通してお知らせするサービスを開始予定です。事業者も車検証閲覧アプリをインストールして、事業に活用する準備を進める必要があります。
認定工場になるには?
記録等事務委託制度の認定工場になるには、「運輸管理部長」もしくは「運輸支局長」の承認を得る必要があります。承認されるには「記録事務代行ポータル」にアクセスし、以下の手順で申請をします。
1.メールアドレスを登録する
2.専用フォームから必要情報を入力する
3.審査結果を待つ
4.審査通過後に発行されるIDとパスワードでログインする
5.「記録事務代行アプリ」をインストールして代行作業を実施する
上記の流れで、認定工場への承認を受けられます。申請条件や必要書類は、記録事務代行ポータルの「申請の準備」のページで確認可能です。スムーズに申請ができるように、先に詳細を確認しておくと良いでしょう。
自動車整備業界に与える影響とは?
車検証のICカード化は、自動車整備業界に大きな影響を与えています。何よりも車検証を変更する必要があるため、その対応業務に追われることが増えています。認定工場でなくても、お客様から車検証の変更について尋ねられるケースが多いため、従業員が基本的な知識を正しく身につけておく必要があります。
また、車検証のICカード化にともなって、各種手続きの手数料が50〜500円程度引き上げられています。その点をお客様に説明することも、自動車整備工場が担う業務となるでしょう。軽自動車の車検証のICカード化は2024年1月からであるため、時期の違いを説明する機会も増える可能性があります。
お客様に対するさまざまなサポートが必要になる点は、普段の業務に大きく影響するでしょう。
1.車検でもIT技術の導入による車検証のIC化・法改正が始まっている
先述したとおり車検証のIC化や法改正によって、車検に影響が出ます。特に指定整備事業者にとっては、運輸支局等への来訪が不要になる一方で、電子車検証のICタグへの記録や検査標章の印刷といった新たな業務を行うことになります。
しかし、従来の車検証を備えた自動車は次回の車検時まで電子車検証へ変更しないため、車検後の登録申請も運輸支局等への来訪が必要です。法改正後はしばらく電子車検証と従来の車検証が混在することになり、車検業務時はどちらの方法で申請を行うか判断が必要です。
2.車検証のICカード化による車両整備業への影響
電子車検証は、今までの車検証のように全ての情報が記載されていないため、全ての情報を確認するためにはアプリを使ってICタグの情報を読み取る必要があります。
車検で入庫した車両の同一性の確認を行うためには、原則として電子車検証のICタグを読み取り、車検証閲覧アプリで確認を行う必要があります。検査を行う自動車検査員が車検証閲覧アプリから印刷した、自動車検査証記録事項でも同一性を確認しても良いとされていますが、これまでの書面の確認と比較すると手間が増えるでしょう。
また、車検証のICタグ内に含まれる個人情報が電子化されるため、今まで以上に個人情報の取り扱いに関する注意が必要です。事業所内でもICタグの読み取りや保存を行うデバイスを限定するなど、新たな運用ルールを設定する必要があるでしょう。
3.点検整備業務以外で車検証のICカード化で期待されること
車検証閲覧アプリは、電子車検証のICタグの情報を確認するだけでなく、他にも様々な機能が備わっています。PDFファイルをダウンロードして保存できるため、パソコンやスマートフォンで車検証の情報を確認したり、外部へ送信したりすることが可能です。
また、車検証閲覧アプリのプッシュ通知機能を活用することで、車検満了日が近づくとユーザーのスマートフォンに通知が来るように設定できます。さらに未実施のリコールの通知もできるため、ユーザー自ら確認することが容易になります。
4.車検証のICカード化後の申請手続き方法
車検証がICカード化後の車検時にオンラインで完結するためには、記録等事務委託制度の「特定記録等事務」の申請が必要です。申請先は運輸監理部長または運輸支局長(軽自動車は軽自動車検査協会)となっており、電子申請(OSS申請)で行います。窓口申請は対象外です。
委託要件は以下のとおりです。
・当該事務を行うのに必要かつ適切な能力を有すること
・適切な組織体制であること
・必要な設備等を有すること
委託要件の詳細は、国土交通省が発表している「特定記録等事務代行等委託要領」をご確認ください。新規の委託申請は令和5年1月から受付しており、「記録事務代行ポータル」というサイトから申請できます。
5.車検へのIT技術導入は自動車整備業界全体に影響する
車検へのIT技術の導入は今回の電子車検証だけでなく、以前から行われていました。自賠責保険や保安基準適合標章の電子化はすでに始まっており、電子車検証を活用するための前提条件となっています。
様々な電子化に伴い、業務の効率化を図れるようになった一方で、新たな知識やツールを取り入れていく必要があります。IT技術導入によって、これまで行ってきた業務がデジタル化されていくため、自動車整備事業者には柔軟な対応が求められるでしょう。
消費者に与える影響について
車検証のICカード化は、自動車を使う消費者にも多くの影響を与えます。車検時にに車検証を発行するまでの時間が短縮されることは、良い影響となります。これまでは指定整備事業者において短時間で車検を行った場合、納車時に新車検証や検査標章の発行が間に合わなかったため、後日に再来店するなどの方法で受け取る必要がありました。電子車検証の場合は、認定工場において車検証のICタグの記録や検査標章の発行を行えるため、1度で完了する機会が増えるでしょう。
車両番号や自賠責保険などのデータをまとめて管理できるため、自動車に関する情報をチェックしやすくなる点もメリットです。
一方で、先に挙げたように手数料が高くなるため、消費者の負担が増加する点はデメリットです。また、現在のところ車検満了日が車検証閲覧アプリでしか確認できないため、不便さを感じる可能性もあります。従来の紙と違ってカード型になるため、高温になる場所で放置したり、折り曲げたりといった行為は避ける必要があります。
まとめ
車検証のICカード化・電子化は、2023年から始まっている制度です。車の所有者はもちろん、事業者側もこの変化を確認し、適切な対応を取る必要があります。事業者は認定工場になることで、車検証のICカード化におけるさまざまな業務を、委託によって受け付けることが可能です。
認定工場となることで、ICカード化したいユーザーに対応可能となります。この機会に申請方法を確認し、委託先の認定工場となることも検討してみてください。
参考記事について
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001482329.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001482329.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001482329.pdf
https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/preparation
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/
https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/
https://www.goo-net.com/magazine/newmodel/by-vehicle-type-information/180829/#toc5
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001482592.pdf
https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/
https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001482592.pdf