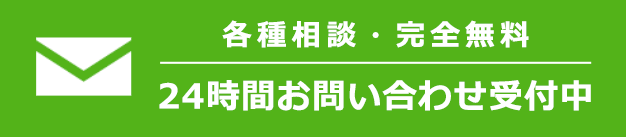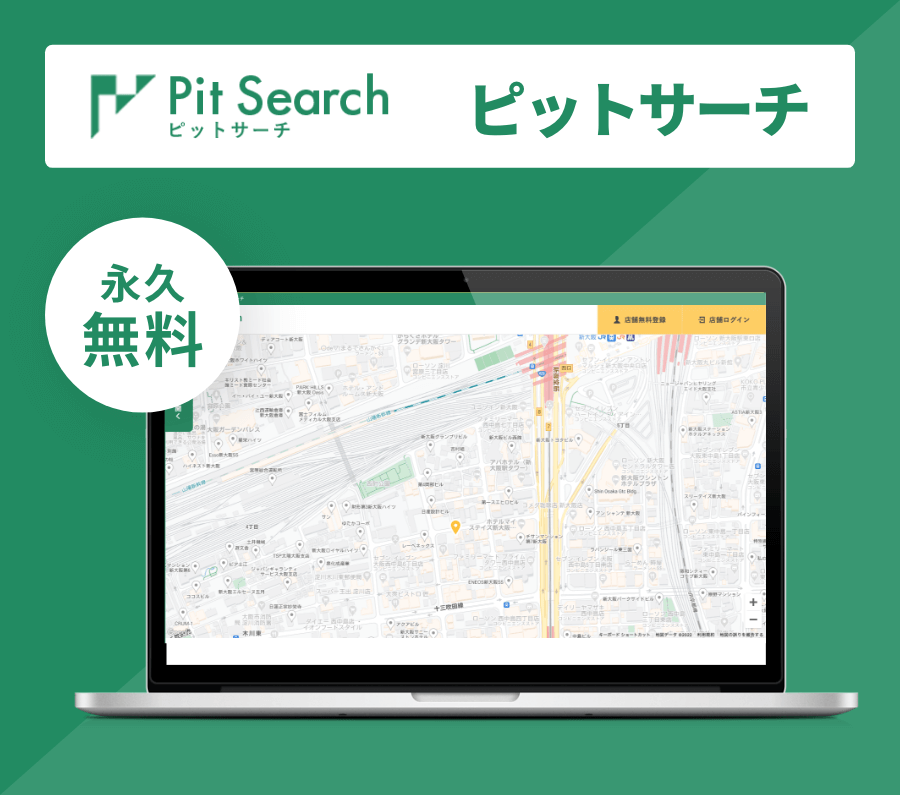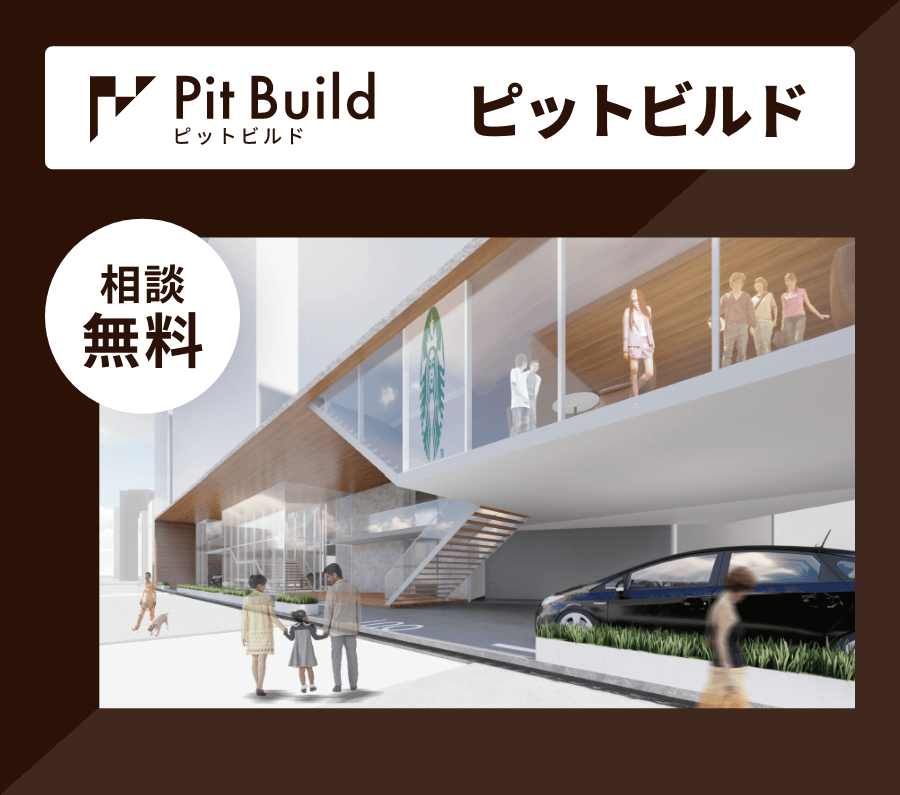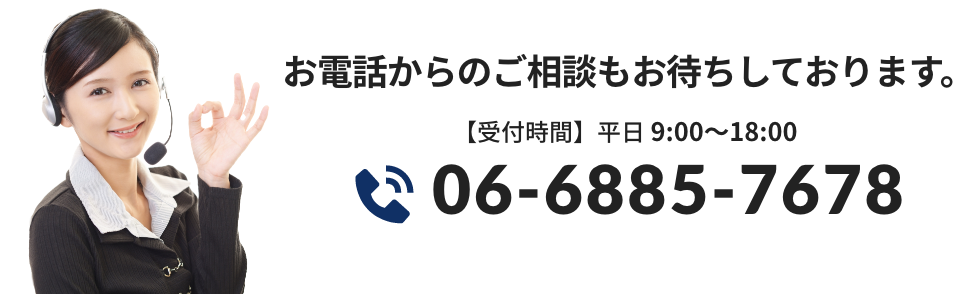諸外国ではEVの普及が急速に進められており、日本も今後さらに普及のペースが早まると予想されます。
そのためにはインフラとなる充電施設の拡充が必要になることから、日本政府や各自治体は補助金等によって充電施設の拡大を後押ししています。
EVの普及に合わせて充電施設を備え、集客などに活かしている商業施設や観光施設が増えてきており、自動車整備工場でも設置が広まるでしょう。
本記事では、自動車整備事業者が充電施設を備えることによってどのようなメリットがあるのか、そのために費用がどの程度かかるのかといったことについて解説します。
EV充電器設置で顧客獲得できる理由

自動車整備工場でも充電施設を設置することで、間接的な利益があります。
ここでは、自動車整備工場が充電施設を設置することで顧客を獲得できる理由について、詳しく解説します。
集客効果
今後ますますEVユーザーが拡大するのは間違いありません。それに伴い自動車整備工場でも、EVの整備などへのニーズが高まっていきます。整備のついでに充電ができるというメリットがあれば、ユーザーにとっても依頼しやすくなります。整備の際には充電が必要なケースもあるため、EVの整備をするのであれば、充電器は備えておくべきです。
例えば、EV充電施設はGoogleMapやナビタイムなどに表示され見つけやすくなっています。そのため、MEO集客にも効果があります。
このように充電設備を備えておくことで地域のユーザーに認知してもらい、充電をきっかけとして整備業務につなげる集客効果が狙えるでしょう。
滞在時間の延長
EVの整備に来た顧客に充電も利用してもらい、整備工場に滞在する時間を延長させて新たな提案の機会を作り出します。店舗にカフェ施設などを設けておくと、充電の待ち時間が過ごしやすくなるため、充電する顧客も増やせるでしょう。そこにチラシなどを設置して待ち時間に見てもらうなど、さまざまな仕掛けが考えられます。
店舗に滞在する時間が長くなれば、新たなビジネスチャンスが発生する可能性が高まります。
会員化による囲い込み
EV整備の顧客を囲い込むために、充電施設利用の会員化を進めるとよいでしょう。
会員には充電ごとにポイントを提供するなどの特典を与え、整備などのサービスに使えるようにします。充電設備を利用する機会が増えれば、それだけ顧客と接するチャンスが拡大しますので、そこで顧客のためになる提案をすれば売上につながる可能性があります。
会員化すると情報発信がしやすくなるというのも大きなメリットです。充電会員の拡大は、他のサービスにつなげるきっかけになるでしょう。
広告のフックに活用
広告を打つ際のフックとして、充電施設があることを活用します。充電会員になるメリットをアピールし、新規の会員として取り込みを狙うとよいでしょう。今後確実に増えるEVユーザーを取り込むためには、広告を通じてEVユーザーに役立つ整備工場であるというイメージを発信し続け、ブランディングしていくことが重要です。
充電のメリットをフックにした広告は、他社との差別化にもつながります。
EV販売や整備とのセット化
今後、整備工場でEVを販売する機会が増えていくと予想されます。EVを販売するのであれば、自店での充電設備が必要です。整備の際に必要になるのはもちろん、納車前に満充電とする顧客サービスのためにも、充電器の設置は必須といえるでしょう。
また、EVの販売や整備と充電をセットにして、便利さやお得感を打ち出すと売りやすくなります。EV販売時には充電会員として取込めるようメリットを打ち出すとよいでしょう。
地球環境への貢献
SDGsの考え方が浸透し、企業活動にも地球環境への貢献が求められるようになっている状況です。多くの企業で環境保全の取り組みがされており、それもブランディングの一部となっています。
充電設備の設置はEV普及を支援することにつながり、温室効果ガスの削減に協力していることになります。整備工場にEV充電設備や太陽光発電装置を設置することで、地球環境保全に貢献する企業であることをアピールする材料となります。
自社のホームページや広告などで発信し、ブランディングに活用するとよいでしょう。
国内外のEV普及状況
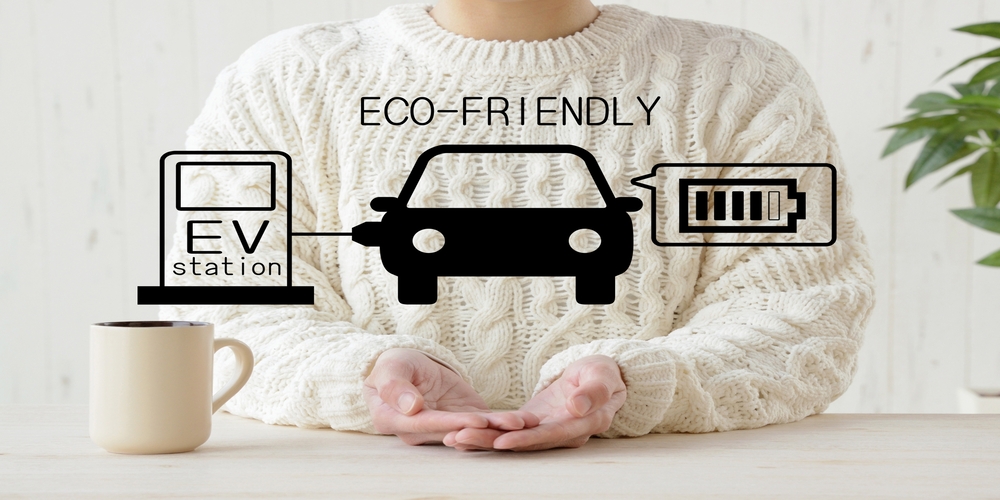
国内外問わずEVは広がっています。特に海外は日本よりもEV化が進んでいる状況です。
ここでは、日本を含む主要な国々でどのようにEV普及が進められているかを解説します。
アメリカ
国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)の発表によると、アメリカにおける2022年の新車販売台数におけるEV・PHEVの比率は約8%でした。前年の販売比率4.5%から2倍近くの伸びとなっており、販売台数は約36万台増加しています。
アメリカ政府は、「2030年までに新車販売のうち50%以上をEVとFCVにする」という目標を発表し、EV化を後押ししている状況です。
アメリカ国内の主要な道路では、50マイル間隔で充電施設の設置を義務付けられ、出入口の1マイル以内への設置も定められています。
EV充電器数は、2022年で12万8000基となっており、2021年と比べると約12%の伸びを示しています。
中国
国際エネルギー機関(IEA)の発表データによると、中国の新車販売台数におけるEV・PHEVの比率は、2022年時点において29%でした。
2020年までの3年間は5%程度でしたが、中国政府の補助金政策もあり2022年には29%と急速に普及が進んでいます。
中国国内で利用できる公共用のEV充電器数は、2022年時点で176万基です。前年と比べて1.5倍と大幅に拡大しています。
イギリス
イギリスの2022年の新車自動車販売台数におけるEV・PHEVの比率は23%です。イギリスでは近年大幅に普及率を伸ばしており、2019年の3%から2020年には11%となり、2022年では23%と急速に普及率を高めています。
イギリス政府は、EV充電設備の設置台数も2030年までに30万台に増やすことを計画し、2035年にはガソリン車の新車販売を禁止することを発表しています。
先進国の中でもイギリスはEV普及が進んでいる国の一つです。
ドイツ
2022年時点のドイツの新車販売台数におけるEV・PHEVの比率は31%です。2019年は約3%でしたが、2020年には13%、2021年には26%、2022年には31%と毎年急速に上昇しています。ドイツ国内で利用できるEV充電器数は、2022年の時点で77,000基です。前年と比べて1.3倍のスピードで増えています。
ドイツを含むEUでは、2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指しています。
そのため、2035年までにガソリンやディーゼルを使うエンジン車の新車販売を禁止することを決定しました。
2030年までにEVの登録台数を最低1,500万台にし、国内の公共EV充電器設置数を100万基まで拡充することを計画しています。
ノルウェー
ノルウェーは、人口550万人の小国ではありますが、2022年のEV普及率88%となった世界最高のEV先進国です。ノルウェー政府は2025年までに新車をすべてゼロエミッション車にする目標を掲げており、EV車購入の後押しとなる減税措置や公共駐車場の無料化などを実施しています。
また、公共交通機関のEV化や充電インフラの整備も進めています。充電設備は2023年末に2万基にまで広がりました。タクシーは2025年にはすべてEVになる予定です。
日本
2023年12月時点でのEVおよびPHEVの新車販売台数は、累計で14万295台です。2024年以降も販売台数の大きな伸びが予想されます。日本のEVおよびPHEVの販売比率は2022年以降上昇しており、現在の販売比率は3.0%前後を維持しています。
また、日本は海外と比べてEVの普及が遅れているものの、日本政府は2035年までに乗用車の新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げています。そのため、インフラとなる充電施設の整備が課題となっている状況です。
今後、ビルやマンションなどの建物を新築する際にはEV充電設備の設置が条例で義務付けられ、2025年4月からは一定規模の新築建築物にはEV充電設備が必須となります。
国内の充電施設普及状況
EV充電施設の数は、2023年12月の時点で2万1,376件に達しています。(※1)
全国のガソリンスタンド数は2022年末の時点で2万店程でしたので、EV充電施設はガソリンスタンドとほぼ同数になっています。初期に設置された充電施設が老朽化したため、2021年に一部撤去されて一時的に減少しましたが、今後も設置数は増加する見込みです。
日本政府は2030年までに30万口を設置することを目標として掲げています。
充電器の種類
EVの充電器には普通充電器と急速充電器の2種類があります。
主要な国内EV・PHVの充電口は2つ設けられていて、小さい方が普通充電用で、大きい方が急速充電用です。
普通充電器と急速充電器の特徴を以下にまとめているので参考にしてみてください。
| 充電器の種類 | 特徴 | 充電器口数 |
|---|---|---|
| 普通充電器 | ・駐車場などに設置していることが多い ・3kW出力や6kW出力のものがほとんどで充電時間が長い | 12,741台 |
| 急速充電器 | ・立ち寄り場所で急速充電可能 ・出力数が20~150kWの充電器で、スピーディーに充電する充電器 ・急速充電器の利用には「1回30分まで」の時間制限があるケースがほとんど | 8,635台 |
充電施設は儲かるのか
大型の商業施設や宿泊施設、ゴルフ場、サービスエリアなどで充電器が設置されているのを見かけるようになりました。EV充電施設を利用した場合、普通充電の1時間あたりの料金相場は300円〜500円、急速充電では1回30分で1,400円〜3,000 円が相場です。これ以上高く設定すると利用されなくなるでしょう。
この価格では充電料金だけを、独立した収益事業にするのは難しいのが現実です。EV充電施設の設置は、単独で収益を考えるのではなく、間接的に利益貢献するツールとして捉えると有効な活用ができます。
自動車整備工場に充電施設を備えるデメリット
自動車整備工場にEV充電施設を備えるには下記のようなデメリットがあります。
- 工事が必要になる
- 各種申請が必要
- 費用がかかる
それぞれ詳しく解説します。
工事が必要になる
EV充電設備を設置するには、充電設備を取り付ける設置工事と、電気を取り込むための電気工事の2つが必要になります。設置場所によっては土木工事をしなければならない場合もあります。また、電気を取り込む場所が分電盤から離れていれば、さらに複雑な工事が必要になるケースもあるため注意が必要です。
通常の設置工事にかかる期間は2〜3週間程度ですが、設置場所によっては追加工事が必要になり、その分工事期間も長くなります。
各種申請が必要
急速充電施設は高圧電力契約が必要で、場合によっては基本料金が高くなることも考えられます。高圧契約になると、「キュービクル(高圧受電設備)」と呼ばれる設備の導入が必要です。設置には機械代も含めて400〜500万円程の費用が必要になり、年間で数十万円の保安コストも発生します。
電力契約によってコストが大きく変わってくるため、どの程度の電気が必要なのかをしっかり見積もることが重要です。
また、充電設備の設置に補助金を利用する場合は申請の準備や事前相談などが必要です。
費用がかかる
充電設備を設置するには、充電器本体の価格と工事費がかかります。
こうした初期費用の他、ランニングコストもかかりますので、複数の業者から見積もりをとり、補助金の活用を含めて、しっかりと資金計画を立てる必要があります。
また、EV充電器の設置に既存設備容量では足りない場合、もう1本、新たに別の線を引き込む「2本引込特例措置」が適用できるなど、充電設備には特例が認められているケースがあります。費用を抑えるためには事前のリサーチが欠かせません。
充電施設の設置にかかる費用
充電施設の設置にかかる費用を以下の表にまとめました。
| 充電器の種類 | 設置費用(設備費+工事費) |
| 普通充電器 | 30万円~100万円 |
| 急速充電器 | 500万円~ |
上記のように多額の費用がかかるものの自動車整備工場に設置することで顧客獲得など多くのメリットがあります。そのため、費用対効果を考えて採算が合うケースが多いです。
とはいえ、導入を検討する際にはしっかりと費用対効果を確認するようにしてください。
設備費
充電設備の本体価格はメーカーによって多少のばらつきはありますが、普通充電器の本体価格は、6kW出力のスタンドタイプの自立型で1台約20万円が相場です。
一方で、急速充電器の本体価格は、30kW〜50kW出力のもので1台約200万円かかります。
設備費用だけでなく工事費用がかかることを理解しておきましょう。
工事費
設置工事費は、普通充電器の場合で40万円〜60万円が相場です。急速充電器の場合は300万円〜500万円といわれており、ケースによってはそれ以上の金額となることがあります。
- 下記のような場合は費用が高くなる可能性があるので注意が必要です。
- 高圧電力契約が必要になる
- 電気を供給している場所からEV充電施設まで15m以上離れている
- ブレーカーに空きがない
事前に業者に見てもらい設置に問題がないか、費用がどのぐらいかかるのかをしっかり確認しておく必要があります。
充電施設の設置に補助金は活用可能か
EV充電器の購入し設置するには「充電インフラ補助金」という国の補助金が使えます。また各自治体でも補助金制度が用意されています。
ここでは、補助金の概要や申請手続きについて解説しましょう。
使える補助金とは
(国が実施する補助金)
EV充電器を設置する際に活用できる国の補助金は「充電インフラ補助金」と呼ばれる補助金で、正式名称は「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」といいます。
充電インフラ補助金で補助金の対象となるのは、充電設備費の50%および工事費用最大100%です。補助金額は急速充電で最大780万円、普通充電で最大135万円となっています。
(自治体が実施する補助金)
国の補助金以外にも各自治体でもEV充電施設の設置に対して補助金を給付しています。
例えば、東京都で事業者が一般開放する充電施設を設置する際に使える補助金として「充電設備普及促進事業(事業用)」があります。
充電設備費については急速充電器の場合は100%、普通充電器の場合は50%まで補助となっており、それぞれ機器ごとの上限があります。工事費用は急速充電器の場合1基あたり上限309万円、普通充電器の場合81万円となっています。
この他にも自治体で独自の補助金制度を用意しているところがあります。要件や金額は自治体によってさまざまですので、自治体のホームページ等で確認してください。
補助金の対象となるもの
補助金の対象となるものは、設備購入費と設置工事費です。
東京都の補助金では、設備購入費と設置工事費に加えて高圧契約に切り替える場合の受電設備改修費も対象となります。
また、公共用の急速充電器を設置する場合には、運営にかかる経費の一部を助成する「充電設備運営費(充電設備運営支援事業)」も利用できます。その場合は電気代、保守費、その他ランニングコストが補助金の対象です。
補助金申請の手続き
国の「充電インフラ補助金」については、一般社団法人 次世代自動車振興センターが窓口となって手続きを行っています。補助金申請の手続きは下記のとおりです。
- 次世代自動車振興センターのホームページで申請の流れ、必要書類を確認する
- オンライン申請システムにて書類を作成し、申請する
- 交付決定を確認
- 充電設備の発注・設置工事を開始
- 設置工事が完了
- 支払いの完了
- オンライン申請システムにて書類を作成
- オンラインで実績報告をする
- 補助金を受領
なお、自治体の補助金に関しては各自治体のホームページを確認してください。
国と自治体の補助金の併用可否
国の補助金を利用した場合でも自治体の補助金も併用可能です。ただし、併用した場合には上限額等に変更がある場合があるため、注意が必要です。
例えば、東京都の補助金を利用し国の補助金を併用する場合は、設備購入費や設備工事費、受変電設備改修費は、国の交付金額分を差引いた額が上限額となります。
まとめ
ここまで解説してきたように、今後日本の自動車の多くがEVになっていくのは間違いありません。
EV対応などはまだ先の話だと思っていると、社会の動きに取り残され淘汰される可能性が高くなります。
近年、国も自治体もEV普及のために補助金などに大きな予算を使って後押しをしています。こうした政策もいつまで続くかわかりません。EV化の流れに乗り遅れないよう、まずは充電施設の設置を検討してみてはいかがでしょうか。
ビズピットでは、自動車整備事業者のEV充電施設の導入についても相談を受け付けています。初回相談は無料ですので、お悩みの自動車整備工場の方は以下からお気軽にご相談ください。
【引用】
※1 経済産業省_電力・ガス取引監視等委員会「日本のEV充電の状況と課題」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/charging_infrastructure/pdf/007_05_00.pdf