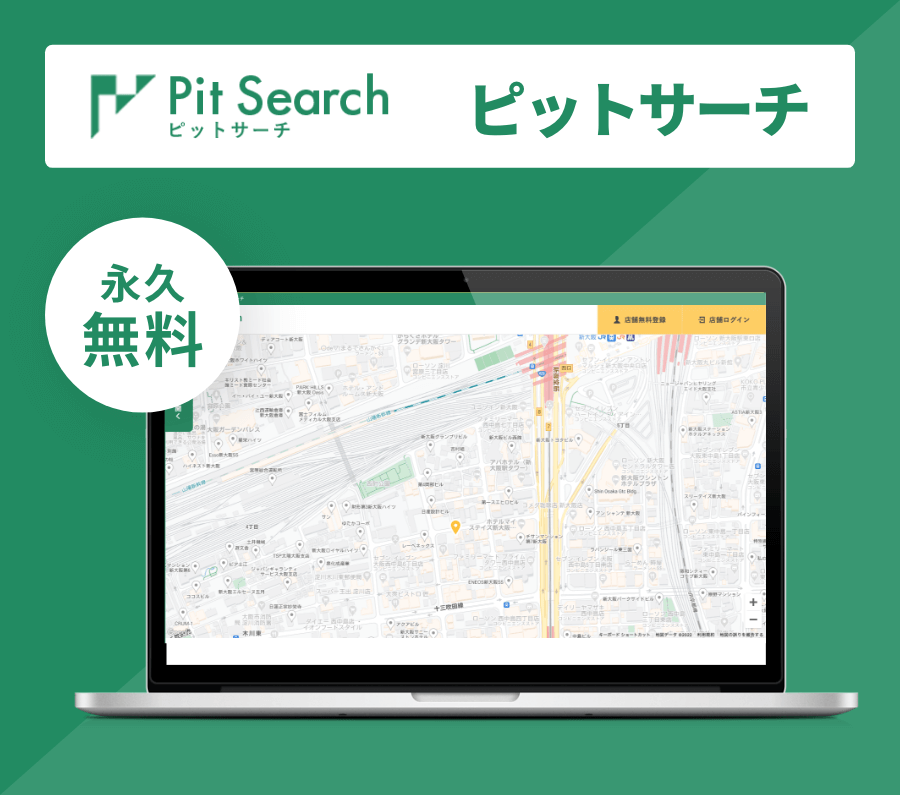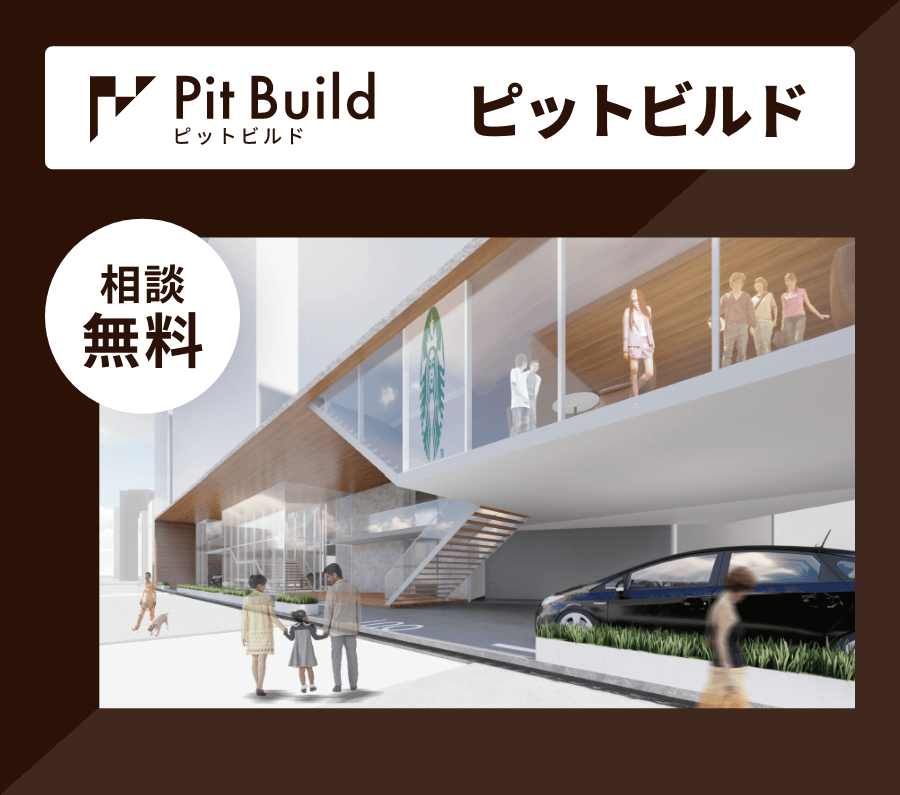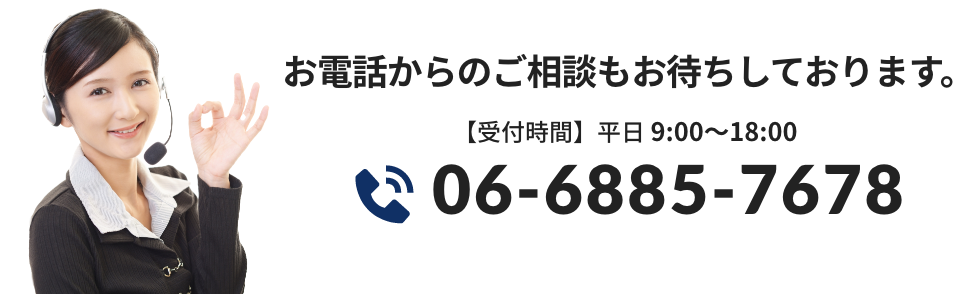そもそも特定整備とは?
「特定整備」とは、従来の「分解整備」に自動ブレーキや自動運転など、電子制御装置に関する整備・改造が追加されたものを指します。分解整備が特定整備に変更された背景として、電子制御装置の普及があります。従来の分解整備の対象装置を取り外さない場合あっても、電子制御装置の不具合が自動車の作動に影響を与える可能性があり、保管基準適合性に大きな影響を与えているケースが増加しているのです。
そこで従来の分解整備に該当する範囲の整備・改造をする場合だけでなく、取り外しをしなくても装置に影響を与える可能性がある電子制御装置の整備・改造をすることが、特定整備の定義に加えられました。
2020年4月1日からすべて特定整備に名称が置き換えられます。基本的に電子制御装置に関する領域以外の整備は、従来の分解整備と同様の方法で実施されます。そのため自動車整備事業者は、従来の分解整備に加えて、特定整備として新たに追加された整備を担当する必要があります。
分解整備と特定整備の違い
まず分解整備とは、自動車整備士が実施する整備業務の1種です。自動車整備士は「点検整備」「緊急整備」「分解整備」といった、3種類の整備を実施します。分解整備に関しては、2級自動車整備士以上の資格が必要になり、高い技術力が求められます。特定整備はこの分解整備の名称を変更し、さらに電子制御装置の整備が新たに追加されたものを指します。
つまり、これまで分解整備と呼ばれていた範囲の整備についても、これからは分解整備ではなく特定整備と呼ばれます。
自動車のエーミングとは?
「エーミング」とは、自動車に搭載された電子制御装置を正しく動かすための校正・調整作業を指します。ASV車には衝突被害軽減ブレーキやセンサー・カメラなどの安全装置が、標準で搭載されています。そういった各種装置が、正常に役割を果たせるように校正・調整するための作業をエーミングと呼びます。
エーミングには「動的エーミング」と「静的エーミング」の2種類があり、それぞれ以下の違いがあります。
動的エーミング:自動車を走行させたまま実施するエーミング作業を指し、特定整備の対象外となる
静的エーミング:自動車を静止させたまま実施するエーミング作業を指し、特定整備に含まれる
今後は自動車整備士が、エーミングによる校正・調整作業を適切に行うことが求められます。
2020年4月から改正特定整備を行うための認証・資格について
2020年4月からの法改正によって、特定整備およびエーミングを行うためには、新たに認証資格を取得する必要があります。すべての整備工場が対象となるため、必要な認証制度と資格を確認し、取得に向けた準備を進めることが求められます。一方で、特定整備への移行にかかる業務負担を考慮して、本制度には4年間の経過措置期間が設定されています。
具体的には2020年3月31日までに、認証が必要となっている電子制御装置の整備を行った経験がある事業所は、2024年3月31日まで、引き続き整備が可能となります。しかし、電子制御装置の整備経験のない事業所に関しては、認証を受ける必要があります。
電子制御装置設備の整備主任者が必要
特定整備・エーミングを実施するには、「電子制御装置整備」の認証が必要になります。認証を受けるには、「適正な作業場所が確保できること」「適正な工具・機器があること」「エーミングを行える整備主任者がいること」が条件となっています。
整備主任者になる方法は、自動車整備士の資格によって以下のように変わります。
1級自動車整備士:そのまま整備主任者になることが可能
2級自動車整備士:資格取得講習の受講と試験の合格が必要
3級自動車整備士:取得が不可能
追加資格を取得して認証を受けることで、整備工場でエーミングが実施できます。
自動車特定整備事業が必要
「自動車特定整備事業」とは、先に解説してきた「特定整備」と同じものです。従来の分解整備に電子制御装置が追加されたもので、具体的には「自動運行装置」「衝突被害軽減制御装置」「自動命令形操舵装置」が含まれます。また、関連装置として「カメラ」「ミリ波レーダー」「赤外線レーダー」も整備か所に該当します。
整備工場は「分解整備のみを行う」「電子制御装置整備のみを行う」「両方の整備を行う」といった、3つのケースを選択できます。
ASV車の普及で今後ますますエーミングが必要になる
ASV車は国土交通省が普及を推進していることもあり、これから普及率がさらに上がっていくでしょう。国産車の新型車はすでに2021年11月から衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)の装着が義務化されており、継続生産車についても2025年12月から義務化されます。
ASV車の普及に伴い、電子制御装置に関わる故障や整備が増えていくことも明白です。特にエーミングはすでに作業をする頻度が増えてきており、フロントガラスの交換やカメラの脱着、コンピュータの交換などの整備を行った場合は必ずエーミングを行う必要があります。
エーミングの増加が中小の自動車整備業者に与える影響
先述したとおり、電子制御装置の整備を行うためには新たな認証資格を取得する必要があります。電子制御装置の整備経験がある事業所には4年の経過措置がありますが、経過措置終了後は電子制御装置を行う全ての自動車整備事業所が認証を受ける必要があります。これからエーミングなどのASV車に関わる整備が増えていく一方で、自動車整備事業所が電子制御装置の認証資格を持っていないことは、業務を行う上で不利に働いてしまいます。
また、エーミングは電子制御装置を作動させるための初期調整であり、正確に行わないとエラーや誤作動を起こす可能性があります。さらに、自動車メーカーや車種によってエーミングに使うツールや作業要領が異なります。特定整備の認証資格を取得するだけでなく、自動車整備士が電子制御装置に関わる新たな知識や技術を習得していく必要があるでしょう。
エーミングが消費者側に与える影響
エーミングが必要になることによって、整備側だけでなく消費者にもさまざまな影響が出ます。例えば特定整備の対象となる部分の整備が追加されるため、これまでよりも整備料金や修理費用が高額になる可能性があります。
また、エーミングを行えるのは認証を受けている事業者か、経過措置の対象となっている事業者だけとなるため、近場で修理ができないケースも増えると予想されます。まだまだ特定整備は消費者に浸透していないため、今後もさまざまな影響が発生すると考えられるでしょう。
エーミングによるコストが高まる分、消費者の車の選び方や基準が変わってくる可能性もあります。事業者は消費者の行動の変化を予測して、柔軟に対応することが求められます。
エーミングに必要なもの
エーミングを行うためには、適切な作業環境が必要です。具体的には以下の3つの条件を満たしている必要があります。
・床が水平で無風であること
・作業場の広さが確保されていること
・周囲に反射物がなく十分な明るさがあること
また、エーミングには以下のツールが必要です。車種やASVのバージョンよって異なる場合があるため、車両ごとの詳細はメーカーの作業要領書をご確認ください。
・水準器:床面の水平度を測定する
・アライメント測定器:車両のアライメントを測定する
・下げ振り:車両の中心線を出すために使用する
・メジャー:ターゲットを設置するために距離を測定する
・ターゲット、リフレクター:エーミング時に車両のカメラが読み込むための標的
・スキャンツール:車両の外部診断機
エーミングは今後も普及していく
ASV車の普及に伴い、エーミングを作業する頻度も上がっていきます。これまではフロントガラスの交換や車両前方の鈑金修理といった修理は単独で完了しましたが、今後は合わせてエーミングの実施が必要になる機会は増えるでしょう。また、電子制御装置自体の故障修理を行った際や、カメラやレーダーの脱着を行った際にもエーミングは必須となります。エーミングはこれからさらに作業頻度が上がっていくため、今後の自動車整備業界にとっては一般的な作業となるでしょう。
しかし、特定整備制度の導入によりエーミングを含む電子制御装置の整備を行うために、新たな認証資格の取得が必要になりました。今後も自動車の技術進歩により、新しい制度や整備技術に対応していく必要があります。自動車整備事業者には、時代の流れに合わせて柔軟な対応が求められるでしょう。
参考記事について
・https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html
・https://seibishi.me/blog/tokuteiseibi/